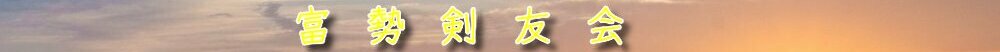*日本剣道形
*日本剣道形
※日本剣道形
練習上の心得
形は打太刀と仕太刀で行い、約束にしたがって一定された形を順序によって練習するのですが、精神的には形にとらわれないで、臨機応変にいずれにも変化できるだけの心技の余裕をもって行なわなければなりません。打太刀はいろいろの攻めを頭に描き、最終的には、約束にしたがって気合を充実して、仕太刀の守りを破る気迫で打ち込みます。これに対して仕太刀はどこから打ち込まれても、これに対応できる先の気位と気迫で攻め勝って、その後、約束にしたがって打つのです。このような心構えで形を練習すれば、そのまま竹刀剣道にも通じ、実生活にも活用できます。
形の実施中は、初めの座礼まで、特に構えをといて後退する時など、寸分も気をゆるめないことが必要です。何よりも肝心なことは、気迫の充実です。
形は打太刀と仕太刀でなりたっていますが、打太刀は客位であり打突動作の相手となり、仕太刀の動作を完全に表示させる師の位です。
仕太刀は主位であり打太刀に動作を行なわせ、それによって自分の動作を完全に表示すると、すなわち門人の位です。それで形では、ふつう上位の者が打太刀をつとめ、あくまでも打太刀が仕太刀をリードして互いの呼吸が合い、気合の充実が肝要で、一挙一動つねに打太刀が始動し、仕太刀は打太刀に従って行動するのです。仕太刀から始動すると呼吸が合わないので、仕太刀から決して始動してはいけません。
仕太刀は、形の上では後に見えるが、気分は常に先であることによって、攻め勝つ気位でなければいけません。気力が攻め勝って、打太刀の技を引き出し、余裕をもち、堂々と正しく打つのです。ややもすると仕太刀は、はじめから待ってばかりいて、打太刀に引きずられ、全然攻め気を失ってしまっています。打太刀、仕太刀''の心構えを笹森順三先生著「一刀流の極意」の中に次ぎのように表現され、その妙をきわめています。
打方(一刀流では、打太刀を打方、仕太刀を仕方としています)「打方は師の位であって、仕方たる弟子を教えるのであるから、打方は常に自らの心気を振り起こして発動し、打突の技を出して攻め、仕方がこれに応ずる心気を育て機会を見ださせ、理にかなう程よい塩合で打たせ、勝つとところはここぞと仕方に覚えさせるのです。」
仕方「仕方は勝つ技を学ぶ位であるが、常に打方の動作に従い応ずるものである。しかし打方の打ち出すのをまっているばかりではなく、心気で、攻め込むところは常に先でなければならない。形に従ては打方にさかわらず、打方のおこす技を尽くさせその尽きたるところを押さえなどして完全に勝ったところで堂々と大きく威を持って強く正しく切るのである。」
形の修練にはまず、形の原本を熟読し、技術を熟練することですが、同時に形の理合を理解しなければいけません。理合をわきまえず、技だけを練習しても、その形は死物にひとしく、理合を知ってはじめて形の意義がうまれます。それに加えて、十分な気合と形の流れにしたがって緩急強弱を習得して、技術のうえに表現しなければなりません。音楽に音律や拍子があるよう に、形にも強さ早さの変化があってこそ、形の妙味が生じ、形が生きてくるのです。往々にして動作が終始、画一的で強弱遅速がなく、形にとらわれすぎて、活気のない気の抜けた形に陥りやすい。つまり技術、気合、緩急強弱、理合が備わってはじめて真の形が生まれてくるので、そのためには百錬自得することが大切です。そうしてはじめて、自然に位や風格も備わってきます。位や格調は永年にわたり根気よく修錬する以外に方法はなく、短日月の間に備わるものではありません。さらに形練習上大事なことは、仕太刀が始めから受け(防)気分でなくて、たえず旺盛な先の気分をわすれないことです。
打太刀、仕太刀''の位置は、道場の構造や指導者によってまちまちで、論拠が不明白でした。そこで昭和四十二年九月、武道館で行なわれた全日本剣道連盟の講習会にさきだっての協議では、正面に向かって右側を上席、すなわち打太刀の位置として、左側を次席すなわち仕太刀の位置とすることにきまり、そのあと、この方法で指導されています。その理由は、宮内庁の礼法では、正面に向かって右が上席で、左が次席であることが明らかになったからです。ただし、これは原則であり、道場の構造や、入口の関係等で、明らかに上席下座が定められている場合は、この限りではありません。
一本目
諸手左上段と諸手右上段との戦い方を示したものです。
打太刀諸手左上段、仕太刀諸手右上段の構えで互いに先の気位で進み、間合に入るや、打太刀は仕太刀の強い先の気位で押され、これを打破すべく機をみて「ヤー」のかけ声とともに仕太刀の正面を柄諸共に打ち込む。仕太刀はすかさず体を後ろに引いて空を打たせ、打太刀の体勢が前傾し崩れたところを「トー」のかけ声で正面を打って勝つ。後、仕太刀は打太刀が少しでも抵抗すれば直ちに打ち下ろす気塊で諸手左上段にとり熱心を示す。打太刀が剣先を下段から中段につけ始めるので、仕太刀も同時に左足を引いて諸手左上段を下ろし、相中段となり、剣先を下げて元の位置にもどる。
註(一)機とは、相手の心と体と術の変わり際に起きるもの、「きざし」です。
註(二)打つということは、切るという意味です。
註(三)仕太刀の残心のとり方打太刀は、剣先を切り下ろした下段の位置のまま、すり足で一歩引くので、仕太刀は十分な気位で打太刀を圧しながら剣先を顔の中心につけ、打太刀がさらに一歩引くのと同時に左足を踏み出しながら諸手左上段に振りかぶり残心を示すのです。
二本目
相中段の際の戦い方を示したものです。
相中段で互いに先の気位で進み、間合に入るや、打太刀は仕太刀の気塊に押され、こらえきれず機をみて「ヤ一」のかけ声とともに仕太刀の右小手を打つ。仕太刀は体を左斜め後方にさばきながら、空を打たせ、剣先を下げて打太刀の刀の下を、半円を描く心持ちで抜いて大きく右足より踏み出して「トー」のかけ声で右小手を打って勝つ。後、形には表さない残心を気位で示しながら、相中段になりながら刀を抜き合わせた位置にもどる。
三本目
一方が下段に構えたとき、相手も下段に構えた場合の戦い方を示したものです。
相下段で構え、互いに先の気位で進み、間合に入るや、互いに気争いとなり剣先を合わせ、自然に相中段になる。そこで打太刀は機をみて「ヤー」のかけ声で仕太刀の胸部(水月)を表突きの要領で突くので、仕太刀は表鎬を利用して柔らかく入れ突きに萎(な)やす(流すの意)と同時に、強く「トー」の声で打太刀の胸部へ突き返す。これに対して打太刀は仕太刀の刀を裏鎬で押さえ(諸手をやや右足を引いて左自然体となる)剣先は仕太刀の咽喉郡につける。このときの気位は双方同等である。位詰(くらいづめ)、仕太刀は、さらに胸部を突く気勢で位詰に左足を踏み出してくるので打太刀は左足を引くと同時に表鏑をもって押さえ(右自然体となる)、剣先は仕太刀の咽喉につけて押さえるけれども、仕太刀の気塊に押されて、これ以上は押さえきれずに構えを解きつつさがる。仕太刀は打太刀の立ち直る隙を与えず、すかさず追いつめて勝つ。仕太刀は剣先を自然に打太刀の顔面の中心につけて残心を示す。そこで双方剣先を合わせ、元の位置にもどる。
四本目
相手が八相に構えたのに対し、脇構えをもって対する戦いの方法を示したものです。
打太刀は八相の構え、仕太刀は脇構えで(大技を示したものなので、小足で互いに間に入る)互いに機をみて双方より大技で、それぞれの構えから上段にかぶり相手の正面を打つ。双方共に相打ちとなり切り結ぶ。(このとき鏑と鏑との交わりとなるが、一両者の腕の高さは稍肩の高さとする)そこから互いに鏑を削るようにして(気塊と気塊との攻め合い)自然に相中投となり、打太刀は機をみて「ヤー」のかけ声で仕太刀の右肺を表突きの要領で突く。これに対して仕太刀は打太刀の突いてくる力を利用して、身体を左へ転ずると同時に(左足を左斜め前に踏み出し右足を左足の後に踏み込む)巻き返し「トー」のかけ声で打太刀の正面を打って勝つ。その後、仕太刀は十分に残心の気位を示すことが大事です。註(一)二本目と同様形に表さない残心なので、十分な気位が必要となる。
五本目
諸手左上段の構えに対し、中段の構えをもって行なう戦い方を示したものです。
打太刀諸手左上段、仕太刀中段の構えで互いに先の気位で進み、間合いに入るや、打太刀は機をみて「ヤー」のかけ声で仕太刀の正面(顎まで切り下げる心持ち)を打つ。これに対して、仕太刀は体を一歩退がりながら直ちに表鎬で摺り上げ、前に一歩踏み出して打太刀の正面を打って勝つ。その後、仕太刀は体を引くが、気で圧しつつ右足を引いて諸手左上段にとり残心示し、さらに左足を引いて中段となり、剣先を合わせ、双方小さく三歩、歩み足で刀を抜き合わせた位置にもどる。
註(一)物打ちの表鏑で摺り上げること。
註(二)摺り上げる動作と打つ動作が二挙動になることなく、一拍子での打ちになること。
六本目
中段の構えに対して、下段の構えをもって戦う方法を示したものです。
打太刀中段、仕太刀下段の構えで互いに先の気位で進み、間合に入るや、仕太刀は機をみて打太刀の両拳の中心を強い気勢で攻め上げる。打太刀は、この気勢を押さえようとして剣先を下げるが、なお仕太刀の気勢を押さえきれずに仕太刀の刀と合おうとする瞬間、右足を引いて諸手左上段にとって間を切ろうとするが、仕太刀はすかさず一歩攻め込むので、打太刀はこの攻めに耐えかねて、直ちに左足を引いて中段に下ろし相中段となる。さらに仕太刀の攻める気勢が強く、打太刀は瞬時に機をみて「ヤー」のかけ声で仕太刀の右小手を打つ。(小枝にて打つ)仕太刀はこれに対し、すかさず小さく裏鏑で摺り上げ、「トー」のかけ声で打太刀の小手を打って勝つのである。その後、打太刀は剣先を下げ、左足から左斜め後ろに大きく引くので、仕太刀は諸手左上段にとり残心を示す。後、打太刀は右足より、仕太刀は大きく右足より元の位置にもどる。
七本目
両者が共に中段に構えたときの戦い方を示したものです。
相中段で互いに先の気位で進み、間合に入るや、打太刀は機をみて仕太刀の胸部を表突きの要領で突く。
仕太刀はこれを左足から体を引くと同時に、諸手を伸ばし、刃先を左斜め下に向け、物打ちの表鏑で打太刀の刀を支える。その後、気勢を充実させながら相中段になる。打人刀は仕太刀の気で押され、それをはね返すように太刀を大きく振りかぶり左・右足と踏み込むと同時に捨身で「ヤー」のかけ声とともに仕太刀の正面を打ち込む。これに対して仕太刀はすかさず右足を右前に開き(右足を右斜め前に出す)、左足を踏み出して、体をすれ違いながら諸手で「トー」のかけ声で打太刀の右胴を打って勝つ。
仕人刀は右膝を折敷いて脇構えにとり、残心を示す。その後、打太刀は仕太刀を引き起こす気待ちで一歩大きく引き、仕太刀は同時に右足を踏みこみ立ち上がって相中段となり、双方気分を弛めることなく位詰め気分で左回りに元の位置にもどる。
小太刀の形三本(打太刀-太刀、仕太刀-小太刀)
一本目
太刀が諸手左上段に構えた際、これに対する小太刀の戦い方を示したものです。
打太刀は、諸手左上段、仕太刀は中段半身の構えで互いに進み、間合に入るや、仕太刀が刀身になり打太刀の手元へつけ入ろうとするので、打太刀は「ヤー」のかけ声で仕太刀の正和を打つ。仕太刀は、これに対してすかさず体を右斜め前に開くと何時に、打太刀の刀を小太刀の表鎬で受け流し、「トー」のかけ声で打太刀の正面を打って勝つ。その後、仕太刀は左足から一歩引いて上段にとり残心を示す。後いったんその場で相中段になってから打太刀・仕太刀ともに刀を抜さ合わせた位置にもどる。この形は「真」の形ともいい、とび込んで、直ちに勝ちを制するものである。
註(1)仕太刀は打太刀の諸手左上段に対しての剣先のつけどころは、顔の中心とする。
二本目
太刀が下段に構えたとき、これに対する小太刀の戦い方を示したものです。
打太刀下段、仕太刀中段半身の構えで間合い入るや、打太刀は下段から刀を徐々に上げて中段になり攻めようとするところを、仕太刀はこれを上より押さえて入身になろうとするので、打太刀は押さえられまいとして、これをはずし脇構えに開く。仕太刀は打太刀の隙を見つけ、速やかに一歩入身で踏み込むので、打太刀は脇構えから大きく頭上に振りかぶって 「ヤー」のかけ声で仕太刀の正面を打つ。仕太刀は直ちにつけ入って裏鎬で受け流し、「トー」のかけ声で打太刀の正面を打って勝ちとなる。
その後、仕太刀は打太刀の二の腕を押さえて剣先を咽喉につけて残心を示す。
この形を「行」の形ともいい、いったん打太刀の下段からの起こりをそうはさせまいと、とがめて、その後勝ちを得るのです。
註(一)構えた際の小太刀の、剣先のつけどころは、打太刀の胸部とする。
註(2)二の腕を押さえとは、関節よりやや上部を押さえ、腕の自由を制すること。
三本目
太刀が中段に構えたとき、小太刀は下段の構えをもって争う方法を示したものです。
打太刀は中段、仕太刀は下段半身の構えで間合に入るや、仕太刀が人身になろうとするので、打太刀は「ヤー」のかけ声で隙のある正面に打ち込む。これに対して仕太刀はその刀を小太刀の表鎬でいったん摺り上げ、そして摺り落とす。
一打太刀の刀を打太刀の斜め後ろに摺り落とすこと。(そのときの剣先は打太刀の体より稍はずれること〉打太刀は摺り落とされたところから直ちに仕太刀の右胴を打ってくるのを、さらに摺り流し「トー」のかけ声で左鏑で摺り込む(そのまま左鏑で打太刀の鍔元に摺り込み)小太刀の刃部のはばきで打太刀の鍔元を制し入身になり、打太刀の二の腕を押さえて勝つのである。その後、打太刀が左斜め後方へ二歩引くので、仕太刀はそのまま攻めて三歩進み右拳を右腰にとり、刀先を右斜め下に向けて、剣先を咽喉につけて残心を示す。この形は「草」の形といわれ、相手の働さを十分にさせた後、捕えて勝ち得るという意味です。
註(一)二の腕を押さえるとは、関節よりやや上部を横から押さえ、腕の自由を制することです。